GL事業
1年生の「明教探究基礎」(本校の総合的な探究の時間)では、現在、課題研究のテーマごとに講座に分かれ、探究活動を行っています。
将来医療関係を志す生徒が集まる本講座では、例年であれば病院訪問などを行っていますが、コロナ禍における代替事業として、今年度は、本校の卒業生でもある小児科医の山本 英一先生にお越しいただき、講演を行っていただきました。
講演後の質疑応答の時間も含め、小児科医の先生から、直接お話を伺うことができ、生徒たちにとっては、大変勉強になる貴重な1時間を過ごすことができました。
山本先生、ありがとうございました。


2年生
1月17日(火)、2年生の学年集会は、生徒意見発表を行い、「緊張しないための方法」と「楽しく過ごすために」をテーマに、2名の生徒が、それぞれ意見を発表しました。



General
冬休み中の12月22日(木)、明教講座を開催しました。
明教講座は、本校の教育方針である「高い知性と豊かな創造性を身に付け、新しい文化の発展に貢献する人間の育成」「高い道義心と公正な判断力を身に付け、人類の福祉増進に貢献する人間の育成」「たくましい気力・体力を身に付け、平和な国家社会の実現に努力する人間の育成」を目指して、社会の第一線で活躍されておられる本校先輩諸氏のものの見方・考え方、生き方に学ぶことを目的としています。
今回は、池内 亜香里さん(平成23年卒、トヨタ自動車株式会社)、森 貴弘さん(平成3年卒、公認会計士)、成松 裕さん(平成14年卒、公認会計士)、 河内 佑太さん(平成16年卒、公認会計士)の4名を講師としてお招きしました。
池内さんは「文系の仕事の選択 ―トヨタでの女性の働き方―」、森さんは「To Make Your Life Better! 公認会計士と考える会計リテラシー」、というテーマで、それぞれ講演をしていただき、後輩である生徒たちに熱い思い、メッセージを伝えていただきました。
生徒たちは、講演会終了後も、受験のこと、将来のことなどについて様々な質問をして、大変有意義な講演会となりました。
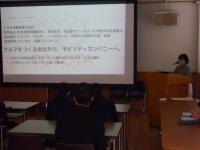



GL事業
東大FW2日目の午前中は、宇野 健司先生の模擬講義を受講し、交換留学のお話を伺ったり、ケーススタディでグループで問題点や解決策について話し合ったりしました。
生徒の発言内容や発表態度の良い所を褒めて伸ばしてくださる先生のお人柄から、生徒たちはコミニュケーションの極意を学び、どんどん自己表出できるようになりました。
午後は大学生主催の留学生との交流会に参加し、英語でお互いの故郷や学校生活について話すなど、コミュニケーションを楽しみました。




